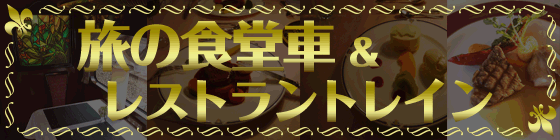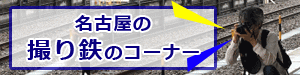●参考になりましたら、シェアしていただけるとサイト運営の励みになります!
桜井線の撮影地にて、淘汰が予想される105系や117系電車などを撮影
主に青春18きっぷを利用した「駅弁」と少し「呑み鉄」、そして時々「撮り鉄」の旅を名古屋からお届けします。今回は置き換えが迫る桜井線105系の撮影記です。
以下、本ページの目次です。以下の、ご興味のある部分をクリックして頂いて、該当部分をご覧下さい。
⇒京終(きょうばて)駅で撮影
⇒駅カフェ「ハテノミドリ」で一服
⇒櫟本(いちのもと)~天理間で撮影
⇒王寺~畠田間で117系を撮影
青春18きっぷシーズン到来です。第1回目は今年1月に撮影活動を実施したものの、曇天で今一歩の結果に終わった桜井線105系の撮影に再度臨むことにしました。
終日好天の予報である2019年3月2日(土)朝7時に東海道本線下り列車で名古屋駅を出発し、米原、京都で乗り換え奈良線を経由して奈良へ行く計画です。
4連の奈良線みやこ路快速奈良行は立ち客多数の混雑で、宇治駅で多少空いて私はドア横の補助席に腰掛けることができました。 なおJR藤森~宇治などの区間では複線化工事が行われており、以前に訪れたことのあるJR藤森~桃山間の「お立ち台」(有名撮影ポイント)は撮影不能となっていました。

奈良線で運用される103系4連は淘汰が進み、残すところあと2編成だそうです。奈良駅で貴重な1本を撮影することができました。しかし残念ながら奈良駅に到着後、車両の差し替えが行われこの103系は入庫する運用でした。(2019.3.2 11:34)

奈良線の普通列車は103系の他、205系と221系が使用されています。205系も首都圏では淘汰が進んでいて、いずれ貴重な存在になることでしょう。(2019.3.2 11:29)
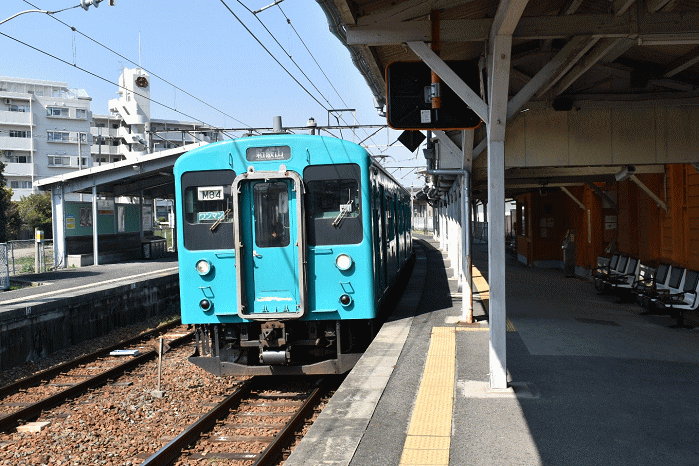
奈良駅の隣にある桜井線京終駅で下車します。ワンマン列車は無人駅では先頭車運転台後ろドアからの降車となりますが、駅のカードリーダーを使用するICカード利用者は先頭車後ろドアからの降車も多く、ここではローカルルールがあるようです。(2019.3.2 11:41)
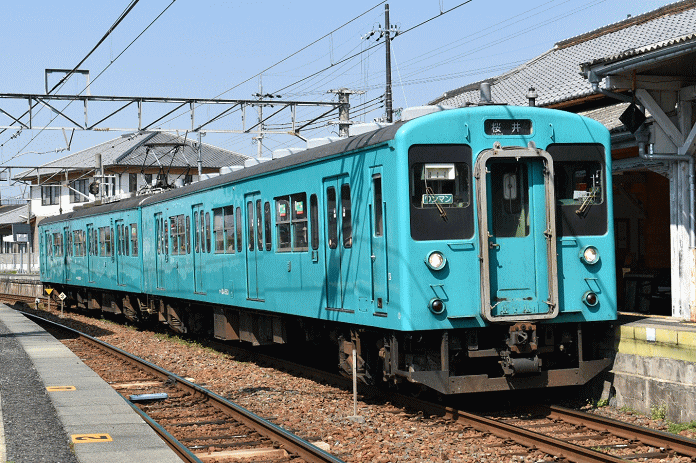
京終駅で次の桜井行列車を撮影。桜井線は日中30分毎の運行で、ここは昼前後が順光となります。(2019.3.2 12:11)
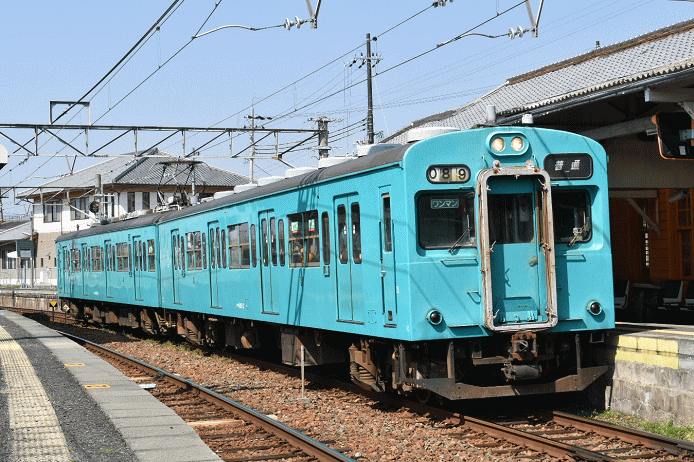
地下鉄直通運転用だったクハ103形1000番台を種車とするクハ104を先頭とする編成がやってきました。和歌山・桜井線で運用される105系19編成中7編成のクハが地下鉄直通用だった貫通扉付の顔となっています。なおちょうどこの時間は停車中の列車正面に架線柱の影が落ちてしまったので、発車直後の少し動いたタイミングで撮影しました。 (2019.3.2 12:41)
JR桜井線京終駅は「奈良町の南の玄関口」とすべく奈良市の手により復元工事が実施されています。2017年(平成29年)から着工し、昨年(2018年)9月に京終駅に降り立った際には、駅舎外観と待合室の整備工事は完了していましたが、旧駅事務室は工事中という状態でした。なお、歴史的町並みの奈良町の一角へは、京終駅から北へ徒歩数分で至ることができます。
今回は駅前広場の工事が進められていたものの、旧駅事務室には観光案内所兼カフェがオープンしていましたので、一服してみることにしました。

1898年(明治31年)に建設された京終駅の駅舎が見事に復元されました。駅前広場の整備工事も最終段階のようで、駅舎横(写真右)では多機能トイレの新築工事が進められていました。駅自体は無人駅で、駅舎内に自動券売機が設置されています。
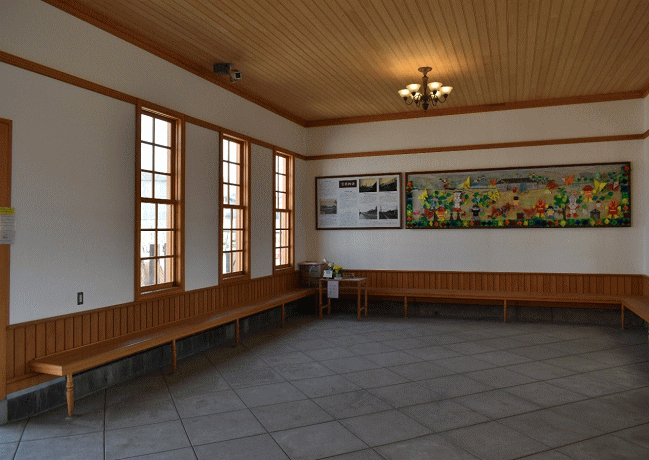
駅待合室としてはもったいない位に素晴らしく整備されました。イベントスペースとしても利用できそうです。

ホーム側から撮影した駅舎です。中央付近の改札口から左側がカフェとなっています。ホームの雰囲気は以前と変わりありません。
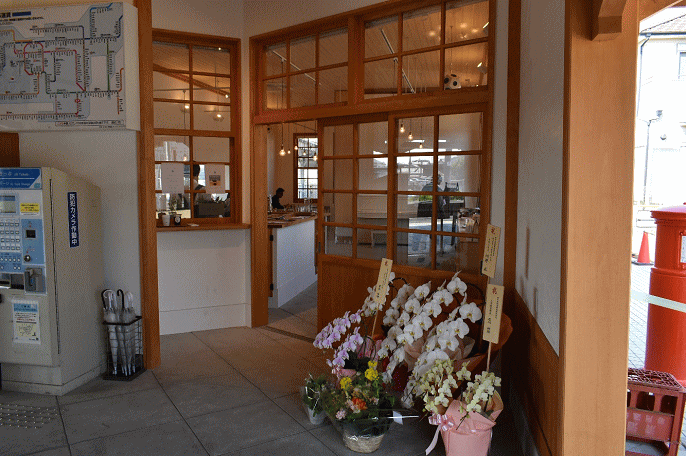
旧駅事務室に誕生した観光案内所とカフェ「ハテノミドリ」の入口です。地元のNPOが運営し2月23日に開所式が行われたそうです。営業時間は3月31までは11:00-15:00・月水定休、4月1日からの営業時間は11:00-19:00・水定休とのことです。

店内はレトロ調に仕上げられています。
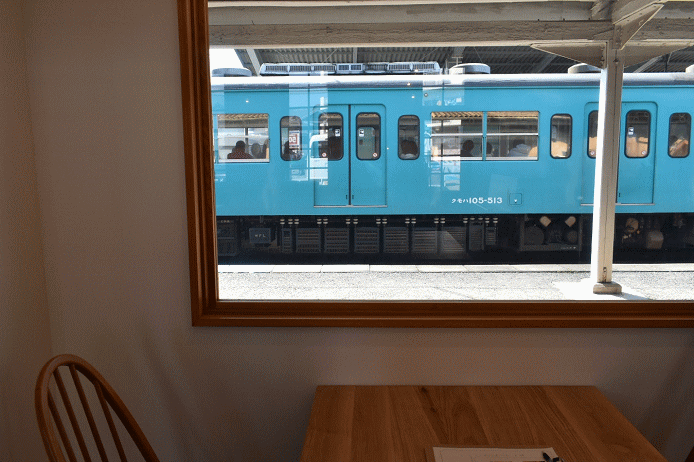
窓側の席はトレインビューを楽しむことができます。写真右側にもトレインビュー席があります。奈良行が到着、トレインビューを楽しみます。このアングルから電車を眺めるとまさに103系そのもので、塗色から京浜東北線にも見えます。
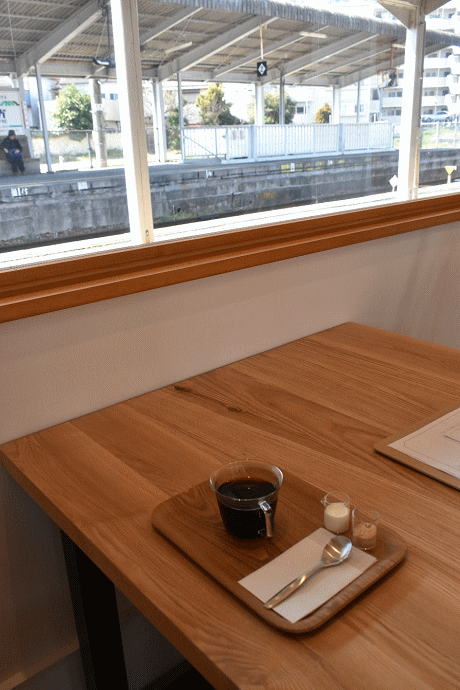
コーヒー(500円)をいただきました。プラスティックのコーヒーカップが少々残念でした。コーヒーなどの飲み物の他、トーストやケーキなど軽食中心のメニューがありました。
京終駅から桜井線列車に乗り櫟本駅に移動、南へ(天理方面)へ約1.2㎞歩いた石上(いそのかみ)踏切で撮影を行います。今年1月にも訪れたものの、暗い曇天で満足な成果を得られなかったため再度訪問したものです。 (撮影地の場所は、リンク先をご覧下さい。)

堂々たる木造駅舎が残る櫟本駅です。例によって無人駅で自動券売機が設置されています。
古い町並みの残る狭い道を歩き、花園寺というお寺の先を右折すると目的地です。本日は晴天とあって10名近くの撮影隊が集まっています。道路からの撮影でアングルを選ばなければ場所に余裕はありますが、時折自動車が通るため注意が必要です。
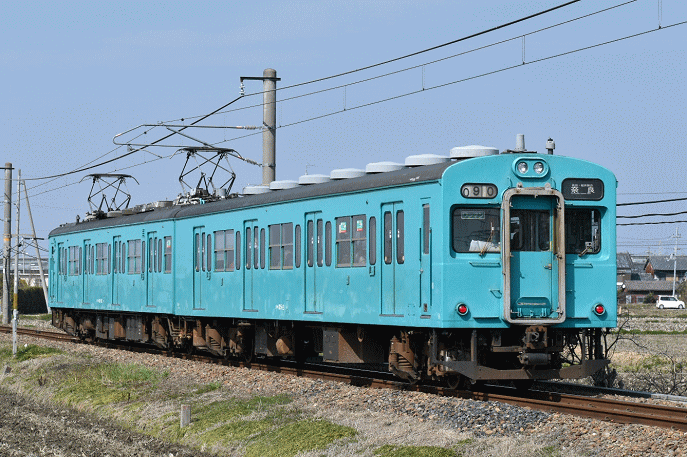
奈良行列車を後追いで撮影。ダブルパンタ、103系1000番台顔の編成が通過しました。奈良で折り返し、30分後には再び撮影できることでしょう。(2019.3.2 13:45)
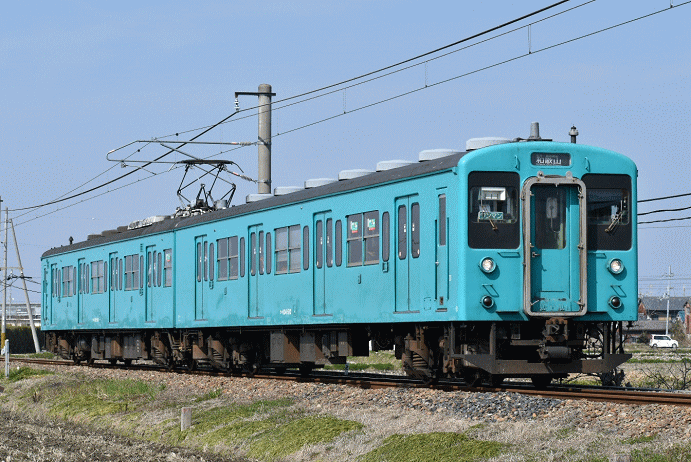
櫟本駅で奈良行と交換した和歌山行が通過します。標準的(?)な105系顔の編成でした。(2019.3.2 13:49)

同じ列車を後追いで撮影します。天理駅側は夏場の午後遅くには順光になりそうですが、路脇に草が生えており一部足回りが隠れてしまします。(2019.3.2 13:49)
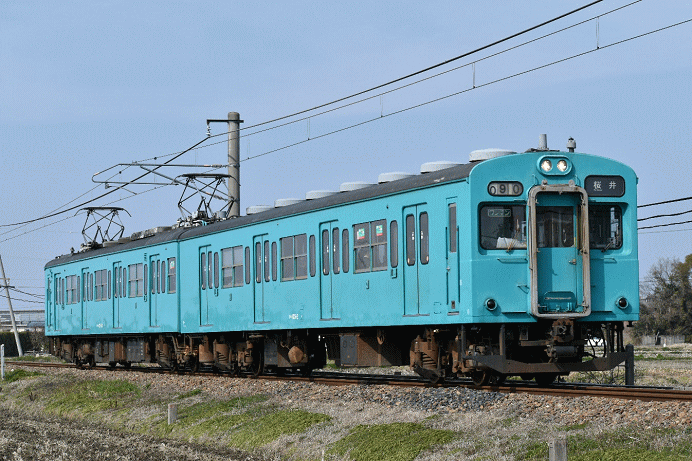
更に30分待ち予定通りやってきたダブルパンタ・103系1000番台顔の編成を撮ることができました。ダブルパンタの編成は5本で、103系1000番台顔の編成はそのうち2本だそうです。(2019.3.2 14:20)
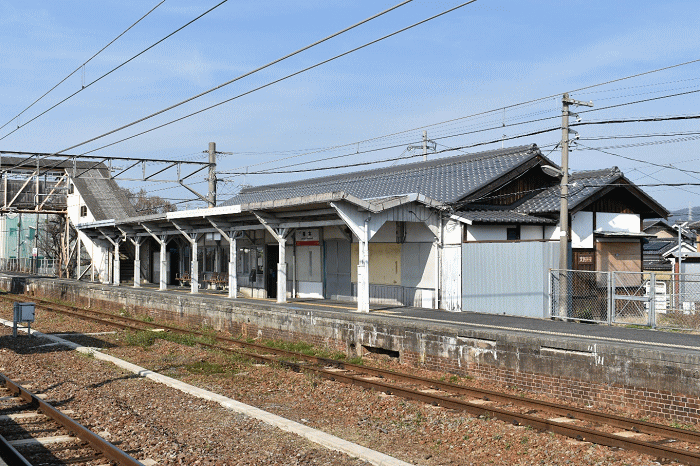
成果に満足し櫟本駅に戻ります。なお撮影ポイントの石上踏切からは、1.5㎞ほど歩くと天理駅に行くこともできます。

櫟本駅に到着する和歌山行列車を撮影。中線があったと思しき駅構内は標識類を気にしなければ、編成写真を撮影することができます。(2019.3.2 14:46)
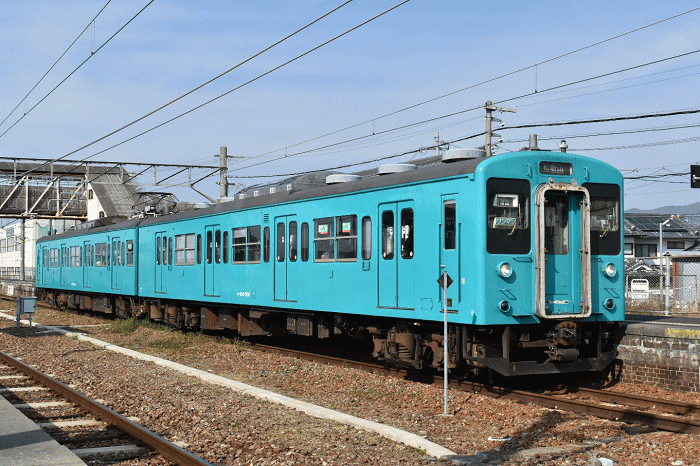
同じ列車を停車中に再び撮影。こちらも標識や信号関係の機器が気になりますが、こればかりは仕方ありません。さて次の目的地は和歌山線の王寺ですが、この列車に乗り高田で乗り換えるより奈良経由の方が早く到着します。(2019.3.2 14:47)
和歌山線では105系、221系の他、朝晩のみ117系が運行されています。新型車両導入に伴い105系とともに置き換えられるようで、是非とも乗っておきたいところです。
しかし乗ってしまうと撮影できず悩ましいのですが、今日は撮影することにします。王寺16:07発の五条行が117系による運行で、場所を選べば順光で撮影できそうです。そこで今回は、王寺駅の南方約1.2㎞にあるで撮影することにします。

王寺駅の自由通路から留置中の117系を撮影。この編成が16:07発の五条行となるようです。余談ながら、王寺駅は列車の発着本数、乗降客ともに多く市街地も発達していますが、市制は施行されておらず「北葛城郡王寺町」という点は意外(斑鳩町はじめ7町で合併構想はあったらしい。)でした。(2019.3.2 15:36)
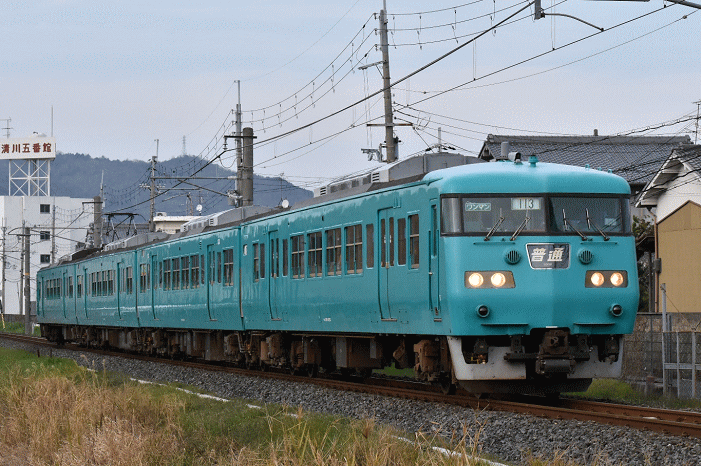
国道168号線を南下し少し東に入ったところにある門前踏切で117系を撮影。架線柱がない側から順光で撮影できるのですが、残念ながら曇ってしまいました。なお撮影場所は比較的交通量の多い道で、歩道がないため要注意です。意外に有名撮影地なのか、本日は5名程の同業者がいらっしゃいました。(2019.3.2 16:09)
117系撮影後、すぐに王寺駅へ戻ります。 復路は撮影場所近くの王寺本町2丁目バス停から、王寺駅行の路線バスを利用しました。
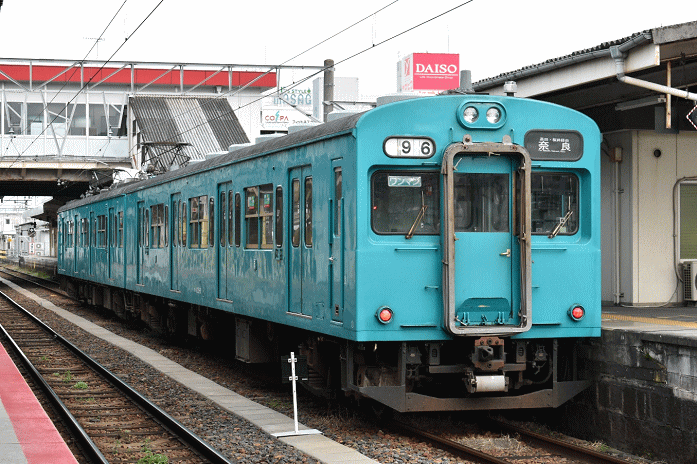
王寺駅では桜井線経由奈良行が停車中、再び103系1000番台顔に出会えました。 (2019.3.2 16:40)

王寺から関西本線経由で名古屋へ向かいます。加茂からはキハ120系ロングシート車による修行旅となりました。(2019.3.2 17:29)
奈良県は駅弁過疎地帯のため、本日は昼食、夕食共に京都駅で仕入れました。京都駅西こ線橋の西改札口近くにある駅弁売店「旅弁当」では、淡路屋の他、草津駅弁や鹿児島・出水駅の松栄軒のお弁当も販売されていて、余りの種類の多さに迷ってしまうほどでした。

昼食は草津駅弁「近江牛すきやき弁当」(㈱南洋軒・1350円)を、京終駅のベンチでいただきました。さすが近江牛は口のなかでとろけるような美味でした。草津駅弁ながら草津駅では予約をしないと入手は難しいようですが、京都駅では南洋軒のお弁当は3種ほど販売されていました。有難いことです。
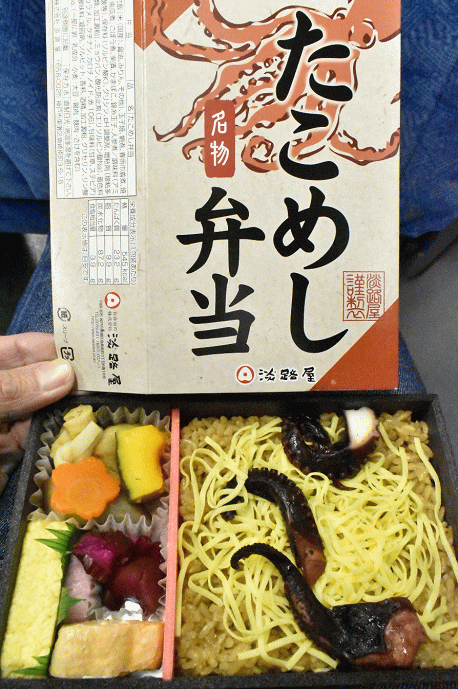
夕食は「たこめし弁当」(㈱淡路屋・1050円)です。関西本線亀山発名古屋行普通列車の快適なクロスシート車内で食したのですが、亀山駅のキオスクはすでに営業時間外でおビールをいただくことはできませんでした。
新型車両導入により快適になる一方で、国鉄世代の私は一抹の寂しさを感じます。国鉄型はいよいよ最終章といった感がありますが、撮る方も乗る方も楽しんでおきたいものです。
(今回の旅はこれでおしまい)
以下、本ページの目次です。以下の、ご興味のある部分をクリックして頂いて、該当部分をご覧下さい。
⇒京終(きょうばて)駅で撮影
⇒駅カフェ「ハテノミドリ」で一服
⇒櫟本(いちのもと)~天理間で撮影
⇒王寺~畠田間で117系を撮影
京終(きょうばて)駅で撮影
青春18きっぷシーズン到来です。第1回目は今年1月に撮影活動を実施したものの、曇天で今一歩の結果に終わった桜井線105系の撮影に再度臨むことにしました。
終日好天の予報である2019年3月2日(土)朝7時に東海道本線下り列車で名古屋駅を出発し、米原、京都で乗り換え奈良線を経由して奈良へ行く計画です。
4連の奈良線みやこ路快速奈良行は立ち客多数の混雑で、宇治駅で多少空いて私はドア横の補助席に腰掛けることができました。 なおJR藤森~宇治などの区間では複線化工事が行われており、以前に訪れたことのあるJR藤森~桃山間の「お立ち台」(有名撮影ポイント)は撮影不能となっていました。

奈良線で運用される103系4連は淘汰が進み、残すところあと2編成だそうです。奈良駅で貴重な1本を撮影することができました。しかし残念ながら奈良駅に到着後、車両の差し替えが行われこの103系は入庫する運用でした。(2019.3.2 11:34)

奈良線の普通列車は103系の他、205系と221系が使用されています。205系も首都圏では淘汰が進んでいて、いずれ貴重な存在になることでしょう。(2019.3.2 11:29)
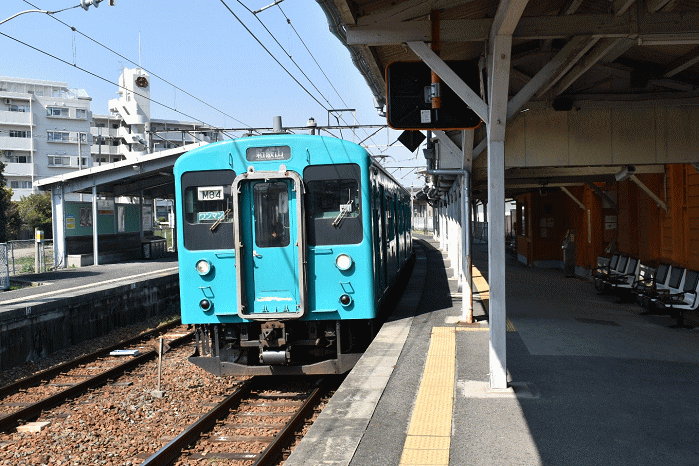
奈良駅の隣にある桜井線京終駅で下車します。ワンマン列車は無人駅では先頭車運転台後ろドアからの降車となりますが、駅のカードリーダーを使用するICカード利用者は先頭車後ろドアからの降車も多く、ここではローカルルールがあるようです。(2019.3.2 11:41)
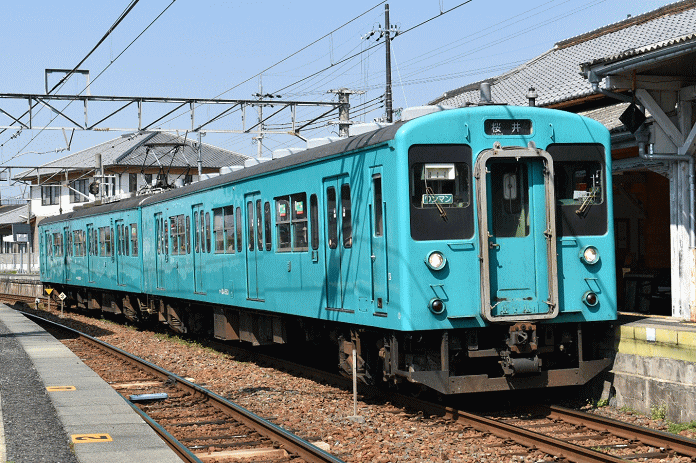
京終駅で次の桜井行列車を撮影。桜井線は日中30分毎の運行で、ここは昼前後が順光となります。(2019.3.2 12:11)
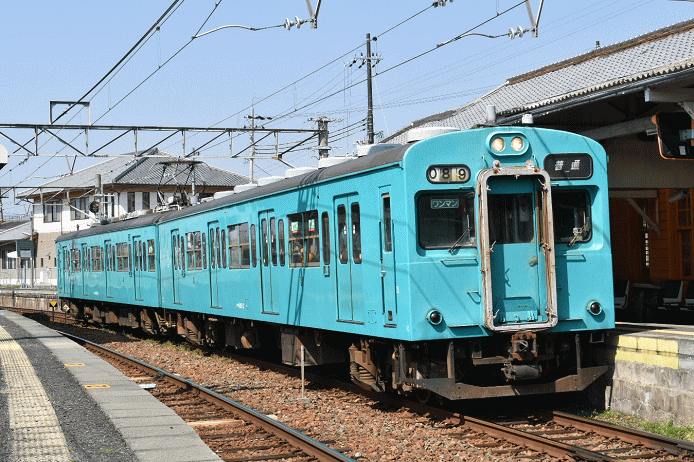
地下鉄直通運転用だったクハ103形1000番台を種車とするクハ104を先頭とする編成がやってきました。和歌山・桜井線で運用される105系19編成中7編成のクハが地下鉄直通用だった貫通扉付の顔となっています。なおちょうどこの時間は停車中の列車正面に架線柱の影が落ちてしまったので、発車直後の少し動いたタイミングで撮影しました。 (2019.3.2 12:41)
駅カフェ「ハテノミドリ」で一服
JR桜井線京終駅は「奈良町の南の玄関口」とすべく奈良市の手により復元工事が実施されています。2017年(平成29年)から着工し、昨年(2018年)9月に京終駅に降り立った際には、駅舎外観と待合室の整備工事は完了していましたが、旧駅事務室は工事中という状態でした。なお、歴史的町並みの奈良町の一角へは、京終駅から北へ徒歩数分で至ることができます。
今回は駅前広場の工事が進められていたものの、旧駅事務室には観光案内所兼カフェがオープンしていましたので、一服してみることにしました。

1898年(明治31年)に建設された京終駅の駅舎が見事に復元されました。駅前広場の整備工事も最終段階のようで、駅舎横(写真右)では多機能トイレの新築工事が進められていました。駅自体は無人駅で、駅舎内に自動券売機が設置されています。
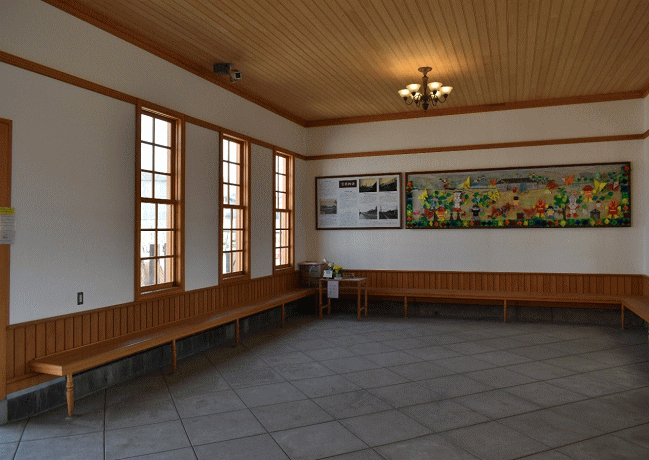
駅待合室としてはもったいない位に素晴らしく整備されました。イベントスペースとしても利用できそうです。

ホーム側から撮影した駅舎です。中央付近の改札口から左側がカフェとなっています。ホームの雰囲気は以前と変わりありません。
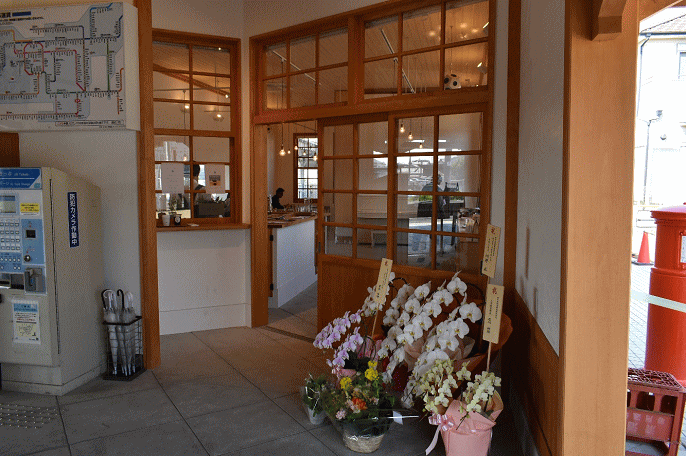
旧駅事務室に誕生した観光案内所とカフェ「ハテノミドリ」の入口です。地元のNPOが運営し2月23日に開所式が行われたそうです。営業時間は3月31までは11:00-15:00・月水定休、4月1日からの営業時間は11:00-19:00・水定休とのことです。

店内はレトロ調に仕上げられています。
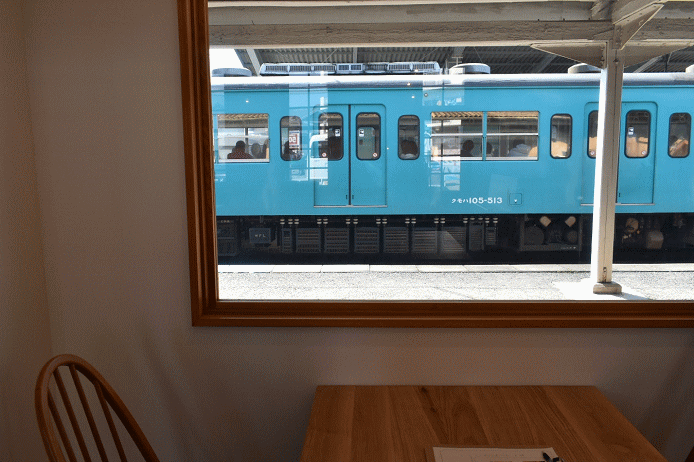
窓側の席はトレインビューを楽しむことができます。写真右側にもトレインビュー席があります。奈良行が到着、トレインビューを楽しみます。このアングルから電車を眺めるとまさに103系そのもので、塗色から京浜東北線にも見えます。
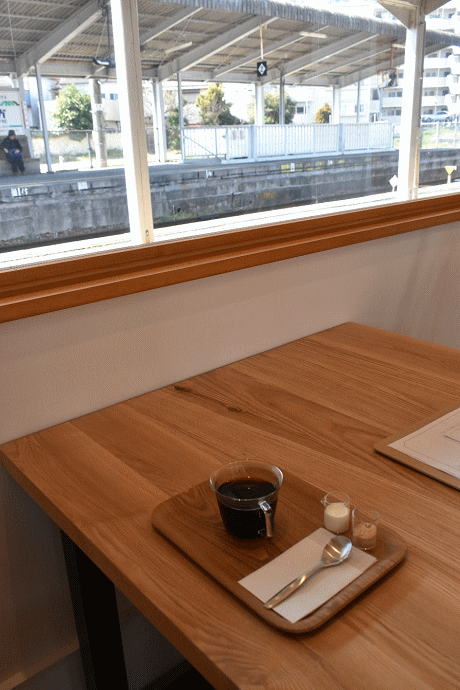
コーヒー(500円)をいただきました。プラスティックのコーヒーカップが少々残念でした。コーヒーなどの飲み物の他、トーストやケーキなど軽食中心のメニューがありました。
櫟本(いちのもと)~天理間で撮影
京終駅から桜井線列車に乗り櫟本駅に移動、南へ(天理方面)へ約1.2㎞歩いた石上(いそのかみ)踏切で撮影を行います。今年1月にも訪れたものの、暗い曇天で満足な成果を得られなかったため再度訪問したものです。 (撮影地の場所は、リンク先をご覧下さい。)

堂々たる木造駅舎が残る櫟本駅です。例によって無人駅で自動券売機が設置されています。
古い町並みの残る狭い道を歩き、花園寺というお寺の先を右折すると目的地です。本日は晴天とあって10名近くの撮影隊が集まっています。道路からの撮影でアングルを選ばなければ場所に余裕はありますが、時折自動車が通るため注意が必要です。
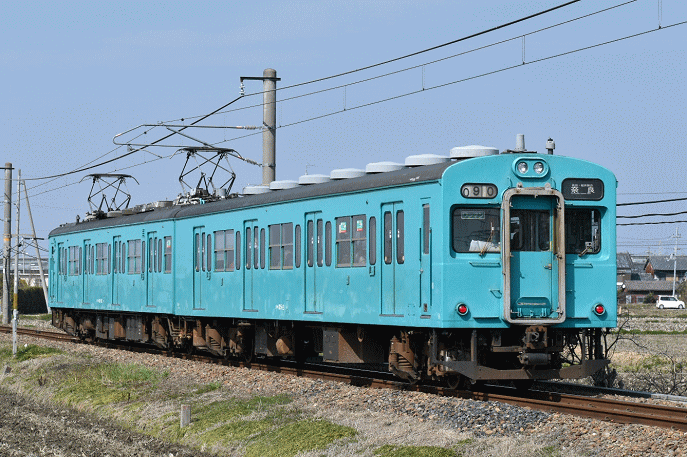
奈良行列車を後追いで撮影。ダブルパンタ、103系1000番台顔の編成が通過しました。奈良で折り返し、30分後には再び撮影できることでしょう。(2019.3.2 13:45)
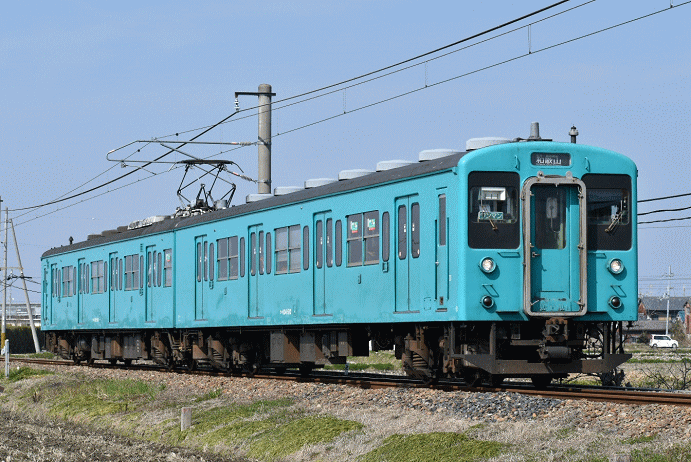
櫟本駅で奈良行と交換した和歌山行が通過します。標準的(?)な105系顔の編成でした。(2019.3.2 13:49)

同じ列車を後追いで撮影します。天理駅側は夏場の午後遅くには順光になりそうですが、路脇に草が生えており一部足回りが隠れてしまします。(2019.3.2 13:49)
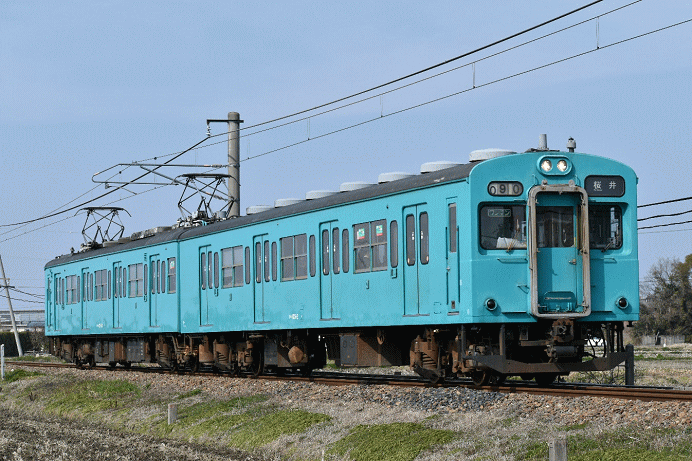
更に30分待ち予定通りやってきたダブルパンタ・103系1000番台顔の編成を撮ることができました。ダブルパンタの編成は5本で、103系1000番台顔の編成はそのうち2本だそうです。(2019.3.2 14:20)
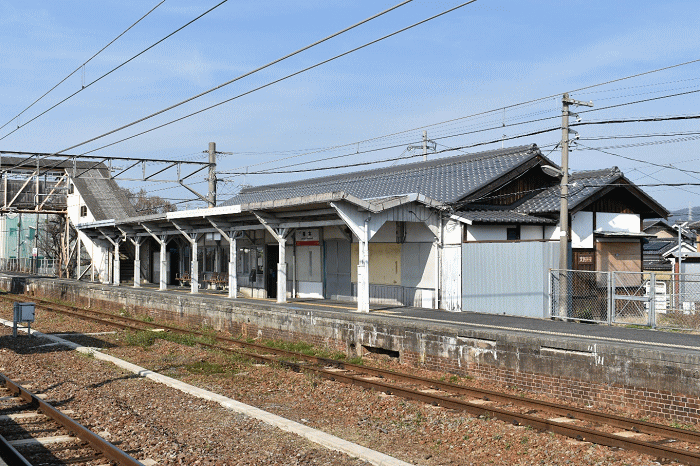
成果に満足し櫟本駅に戻ります。なお撮影ポイントの石上踏切からは、1.5㎞ほど歩くと天理駅に行くこともできます。

櫟本駅に到着する和歌山行列車を撮影。中線があったと思しき駅構内は標識類を気にしなければ、編成写真を撮影することができます。(2019.3.2 14:46)
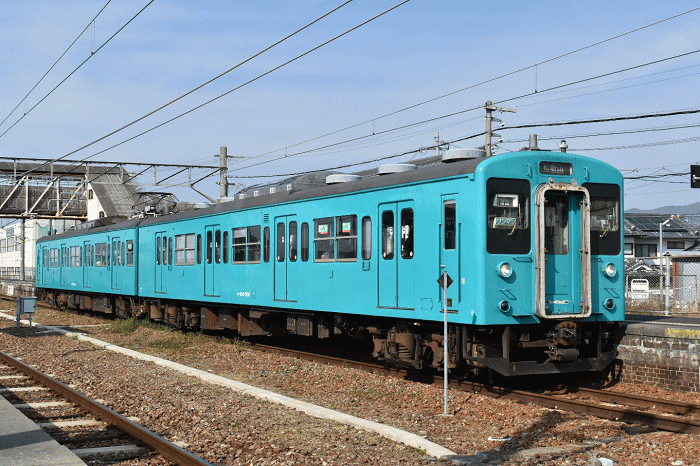
同じ列車を停車中に再び撮影。こちらも標識や信号関係の機器が気になりますが、こればかりは仕方ありません。さて次の目的地は和歌山線の王寺ですが、この列車に乗り高田で乗り換えるより奈良経由の方が早く到着します。(2019.3.2 14:47)
王寺~畠田間で117系を撮影
和歌山線では105系、221系の他、朝晩のみ117系が運行されています。新型車両導入に伴い105系とともに置き換えられるようで、是非とも乗っておきたいところです。
しかし乗ってしまうと撮影できず悩ましいのですが、今日は撮影することにします。王寺16:07発の五条行が117系による運行で、場所を選べば順光で撮影できそうです。そこで今回は、王寺駅の南方約1.2㎞にあるで撮影することにします。

王寺駅の自由通路から留置中の117系を撮影。この編成が16:07発の五条行となるようです。余談ながら、王寺駅は列車の発着本数、乗降客ともに多く市街地も発達していますが、市制は施行されておらず「北葛城郡王寺町」という点は意外(斑鳩町はじめ7町で合併構想はあったらしい。)でした。(2019.3.2 15:36)
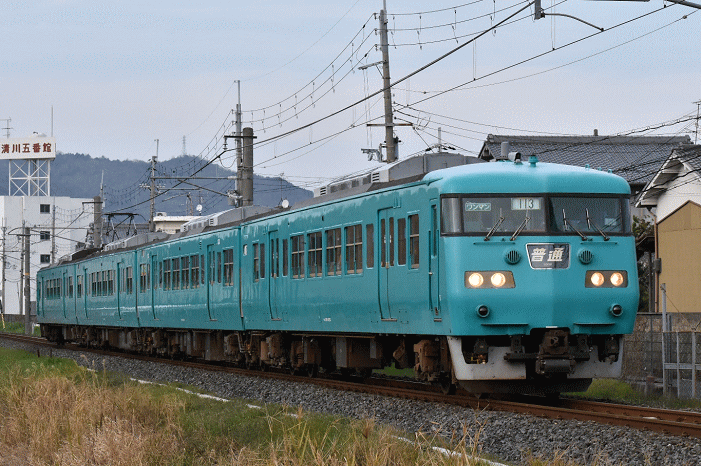
国道168号線を南下し少し東に入ったところにある門前踏切で117系を撮影。架線柱がない側から順光で撮影できるのですが、残念ながら曇ってしまいました。なお撮影場所は比較的交通量の多い道で、歩道がないため要注意です。意外に有名撮影地なのか、本日は5名程の同業者がいらっしゃいました。(2019.3.2 16:09)
117系撮影後、すぐに王寺駅へ戻ります。 復路は撮影場所近くの王寺本町2丁目バス停から、王寺駅行の路線バスを利用しました。
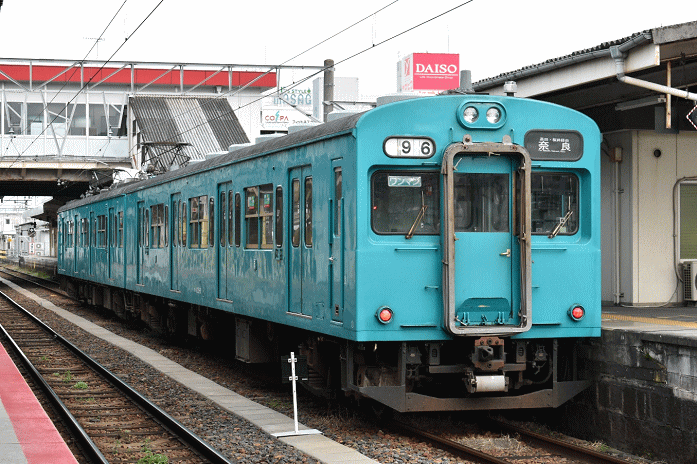
王寺駅では桜井線経由奈良行が停車中、再び103系1000番台顔に出会えました。 (2019.3.2 16:40)

王寺から関西本線経由で名古屋へ向かいます。加茂からはキハ120系ロングシート車による修行旅となりました。(2019.3.2 17:29)
本日いただいた駅弁
奈良県は駅弁過疎地帯のため、本日は昼食、夕食共に京都駅で仕入れました。京都駅西こ線橋の西改札口近くにある駅弁売店「旅弁当」では、淡路屋の他、草津駅弁や鹿児島・出水駅の松栄軒のお弁当も販売されていて、余りの種類の多さに迷ってしまうほどでした。

昼食は草津駅弁「近江牛すきやき弁当」(㈱南洋軒・1350円)を、京終駅のベンチでいただきました。さすが近江牛は口のなかでとろけるような美味でした。草津駅弁ながら草津駅では予約をしないと入手は難しいようですが、京都駅では南洋軒のお弁当は3種ほど販売されていました。有難いことです。
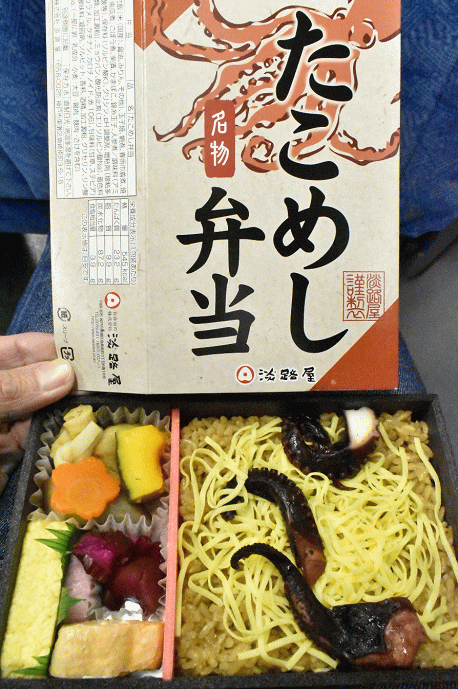
夕食は「たこめし弁当」(㈱淡路屋・1050円)です。関西本線亀山発名古屋行普通列車の快適なクロスシート車内で食したのですが、亀山駅のキオスクはすでに営業時間外でおビールをいただくことはできませんでした。
新型車両導入により快適になる一方で、国鉄世代の私は一抹の寂しさを感じます。国鉄型はいよいよ最終章といった感がありますが、撮る方も乗る方も楽しんでおきたいものです。
|
【乗車データ】 ・名古屋8:00→米原9:10 サハ313-5314 8両 ・米原9:19→京都10:13 クモハ223-3011 12両 ・京都10:33→奈良11:18 クハ221-21 4両 ・奈良11:38→京終11:41 クハ104-503 2両 ・京終13:11→櫟本13:19 クモハ105-506 2両 ・櫟本14:57→奈良15:07 クハ105-8 2両 ・奈良15:17→王寺15:32 クハ221-4 8両 ・王寺本町2丁目16:13→王寺駅16:19 (奈良交通バス) ・王寺16:49→加茂17:20 クモハ221-63 8両 ・加茂17:48→亀山19:05 キハ120-11 2両 ・亀山19:13→名古屋20:30 クモハ313-1308 5両 |
(今回の旅はこれでおしまい)