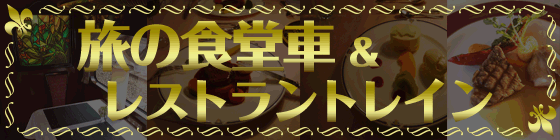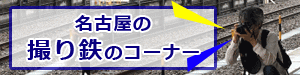●参考になりましたら、シェアしていただけるとサイト運営の励みになります!
奈良線と京都鉄道博物館(その1)・・・近鉄&京阪乗り継ぎで名古屋から京都へ
主に青春18きっぷを利用した「駅弁」と少し「呑み鉄」、そして時々「撮り鉄」の旅を名古屋からお届けします。今回は、103系の置き換えが始まった奈良線と京都鉄道博物館の旅です。
⇒近鉄&京阪乗り継ぎで名古屋から京都へ(←今ここ)
⇒奈良線は丹波橋駅付近の撮影地で撮影
⇒京都駅弁、懐かしの「萩乃家」を訪ねる
⇒梅小路公園で京都市電に乗車
⇒京都鉄道博物館・本館を訪問した記録
⇒京都鉄道博物館・扇形車庫に感動
奈良線を中心として活躍する黄緑色の103系。大阪環状線への新型車両導入に伴い、朝晩の大阪乗り入れ運用が無くなる等、いよいよ置き換えが開始されるようです。・・・とはいえ、今日まで初期型の低窓車が活躍してきたこと自体が、奇跡とも思えますが。

【思い出の写真】昨年(2016年)までは、平日朝晩のみ大阪環状線への乗り入れ運用がありました。103系初期型の区間快速運用も思い出に。 (2015.5.25 8:08 福島)
そんな奈良線へは近日中に訪れたいと考えていたところ、同僚から出張の予定が変わり、近鉄の「名阪まる得きっぷ」が2枚余ってしまったとのこと。有効期限が迫っていますが、買い取ることにしました。
なおこの切符、名古屋⇔大阪の特急券込みの片道回数券タイプなのですが、バラでの使用可、金券屋では1枚3,350円前後で販売されています。所定は 4,260円なので、かなりお値打ちで、名古屋人には愛用者が多いです。
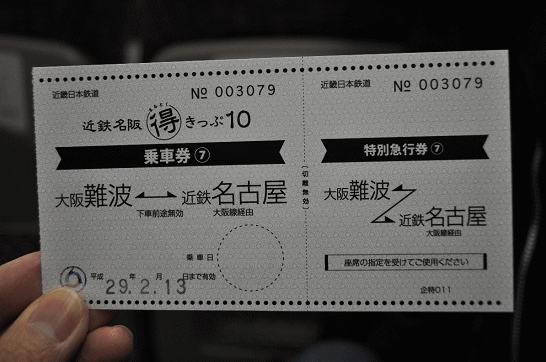
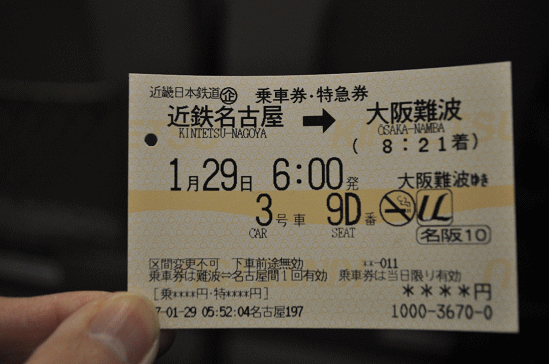
金券屋でバラ売りの回数券を購入して、駅の窓口で座席の指定を受けると良いでしょう。
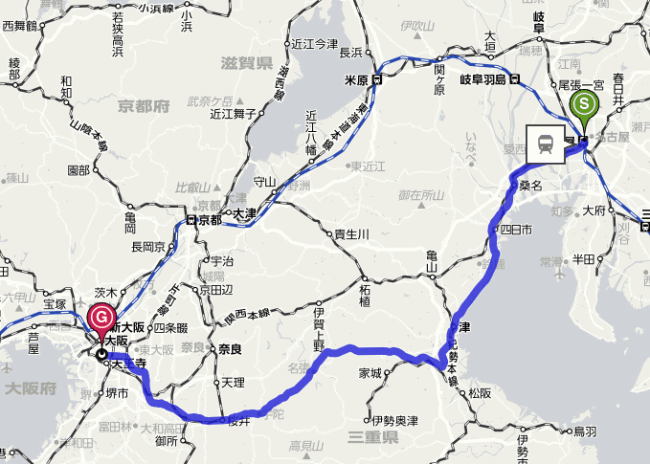
2017年1月29日(日)、早朝6:00に近鉄名古屋駅を出発します。奈良線の撮影は京都市内で予定しています。京都へ行くのに大阪経由とは時間的、費用的に非効率ですが、前述の理由により近鉄特急利用となったため仕方がありません。

早朝の近鉄名古屋駅は、さすがに閑散としています。
名阪近鉄特急の旅は、車窓風景に飽きることがありません。特に伊勢中川(列車自体は短絡線を通過し停車しません。)付近から桜井付近までの、特に青山峠前後の山中を高速走行する独特の感覚は近鉄特急ならではで、私はいつも楽しみにしています。
・・・が、今日は 6:50発車の津駅付近から意識がなくなり、名張付近で先日の大雪の名残を見たような気がしたものの、気が付いたら大阪平野を走行中でした。快眠=快適ということでしょうが、誠に残念至極でございました。

8:21、大阪難波到着。同じホームから阪神電車が発車するので、神戸やUSJへ行くのも便利です。私は地下鉄御堂筋線に乗り換えて、淀屋橋へ。
淀屋橋からは京阪特急に乗ります。これから向かう奈良線の撮影地の最寄り駅は丹波橋で、特急停車駅ですが、ちょうど停車中の列車は一日数本運転されている「快速特急」。
大阪市内京橋を発車すると京都の七条まで停車しません。まさに昔の京阪特急復活です。七条から丹波橋まで戻るとなると費用、時間とも余分にかかってしましますが、程よく空いていることもあり、乗車することにしました。

淀屋橋9:00発の快速特急出町柳行、ヘッドマーク付です。快速特急、特急を合わせて 10分毎の運行で便利です。

大阪難波駅で購入した「だし巻きと穴子のお弁当」(㈱淡路屋・1,050円)をいただきます。一見、薄味に見えた穴子も食べてみると、しっかりとした味わいでした。JRの新快速や快速列車に比べて、座席指定制でない私鉄特急で駅弁を食べるのは何故か抵抗があります。しかし今日は空いていたので幸いでした。
18きっぷ利用が多い昨今、久々に乗車した京阪本線の車窓は新鮮でした。また車内もJRより豪華で、所要時間は兎も角、快適性や料金は新快速に決して劣らないと感じました。
七条からの折り返しの準急電車は収納式座席を装備し、朝ラッシュ時5扉、通常3扉の5000系に乗車。1970年(昭和45年)から1980年(昭和55年)の製造ながら、事故廃車の1両を除く全車両が健在です。

丹波橋駅に停車中の京阪5000系。通常は5扉のうち3扉を使用。

5000系のラッシュ時用の扉です。収納式座席が面白い構造です。
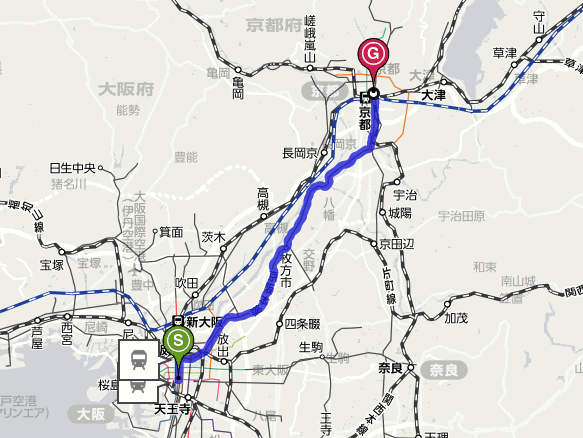
⇒次:奈良線は丹波橋駅付近の撮影地で撮影
⇒近鉄&京阪乗り継ぎで名古屋から京都へ(←今ここ)
⇒奈良線は丹波橋駅付近の撮影地で撮影
⇒京都駅弁、懐かしの「萩乃家」を訪ねる
⇒梅小路公園で京都市電に乗車
⇒京都鉄道博物館・本館を訪問した記録
⇒京都鉄道博物館・扇形車庫に感動
奈良線を中心として活躍する黄緑色の103系。大阪環状線への新型車両導入に伴い、朝晩の大阪乗り入れ運用が無くなる等、いよいよ置き換えが開始されるようです。・・・とはいえ、今日まで初期型の低窓車が活躍してきたこと自体が、奇跡とも思えますが。

【思い出の写真】昨年(2016年)までは、平日朝晩のみ大阪環状線への乗り入れ運用がありました。103系初期型の区間快速運用も思い出に。 (2015.5.25 8:08 福島)
近鉄特急で出発、大阪難波まで乗車
そんな奈良線へは近日中に訪れたいと考えていたところ、同僚から出張の予定が変わり、近鉄の「名阪まる得きっぷ」が2枚余ってしまったとのこと。有効期限が迫っていますが、買い取ることにしました。
なおこの切符、名古屋⇔大阪の特急券込みの片道回数券タイプなのですが、バラでの使用可、金券屋では1枚3,350円前後で販売されています。所定は 4,260円なので、かなりお値打ちで、名古屋人には愛用者が多いです。
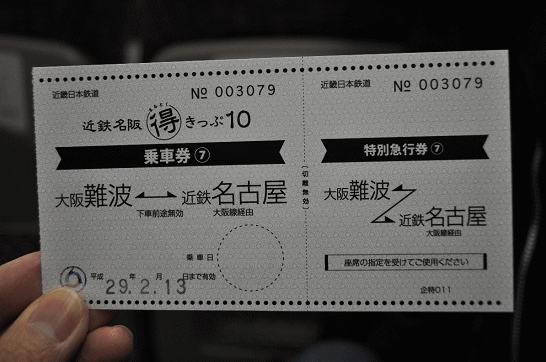
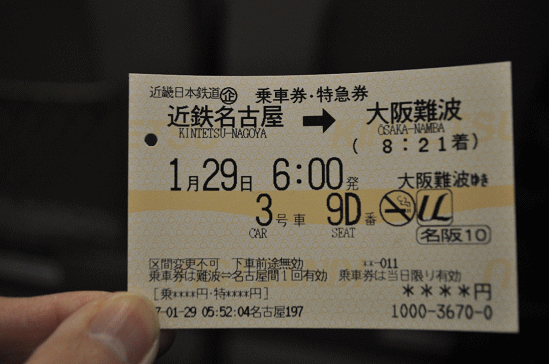
金券屋でバラ売りの回数券を購入して、駅の窓口で座席の指定を受けると良いでしょう。
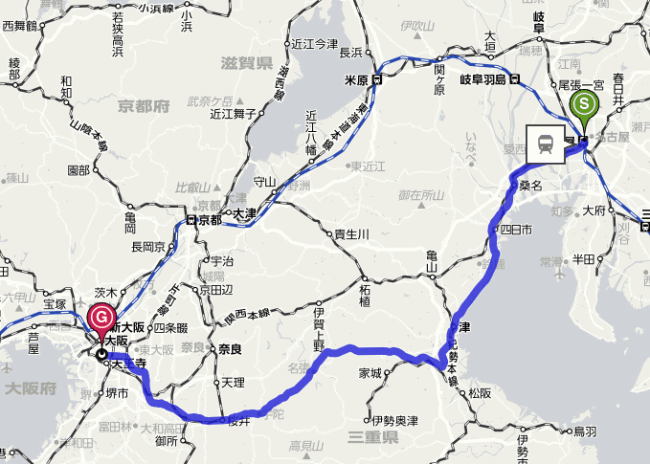
2017年1月29日(日)、早朝6:00に近鉄名古屋駅を出発します。奈良線の撮影は京都市内で予定しています。京都へ行くのに大阪経由とは時間的、費用的に非効率ですが、前述の理由により近鉄特急利用となったため仕方がありません。

早朝の近鉄名古屋駅は、さすがに閑散としています。
名阪近鉄特急の旅は、車窓風景に飽きることがありません。特に伊勢中川(列車自体は短絡線を通過し停車しません。)付近から桜井付近までの、特に青山峠前後の山中を高速走行する独特の感覚は近鉄特急ならではで、私はいつも楽しみにしています。
・・・が、今日は 6:50発車の津駅付近から意識がなくなり、名張付近で先日の大雪の名残を見たような気がしたものの、気が付いたら大阪平野を走行中でした。快眠=快適ということでしょうが、誠に残念至極でございました。

8:21、大阪難波到着。同じホームから阪神電車が発車するので、神戸やUSJへ行くのも便利です。私は地下鉄御堂筋線に乗り換えて、淀屋橋へ。
京阪の快速特急に乗車して、駅弁「だし巻きと穴子のお弁当」を頂く
淀屋橋からは京阪特急に乗ります。これから向かう奈良線の撮影地の最寄り駅は丹波橋で、特急停車駅ですが、ちょうど停車中の列車は一日数本運転されている「快速特急」。
大阪市内京橋を発車すると京都の七条まで停車しません。まさに昔の京阪特急復活です。七条から丹波橋まで戻るとなると費用、時間とも余分にかかってしましますが、程よく空いていることもあり、乗車することにしました。

淀屋橋9:00発の快速特急出町柳行、ヘッドマーク付です。快速特急、特急を合わせて 10分毎の運行で便利です。

大阪難波駅で購入した「だし巻きと穴子のお弁当」(㈱淡路屋・1,050円)をいただきます。一見、薄味に見えた穴子も食べてみると、しっかりとした味わいでした。JRの新快速や快速列車に比べて、座席指定制でない私鉄特急で駅弁を食べるのは何故か抵抗があります。しかし今日は空いていたので幸いでした。
久々に乗車した京阪本線の車窓は新鮮
18きっぷ利用が多い昨今、久々に乗車した京阪本線の車窓は新鮮でした。また車内もJRより豪華で、所要時間は兎も角、快適性や料金は新快速に決して劣らないと感じました。
七条からの折り返しの準急電車は収納式座席を装備し、朝ラッシュ時5扉、通常3扉の5000系に乗車。1970年(昭和45年)から1980年(昭和55年)の製造ながら、事故廃車の1両を除く全車両が健在です。

丹波橋駅に停車中の京阪5000系。通常は5扉のうち3扉を使用。

5000系のラッシュ時用の扉です。収納式座席が面白い構造です。
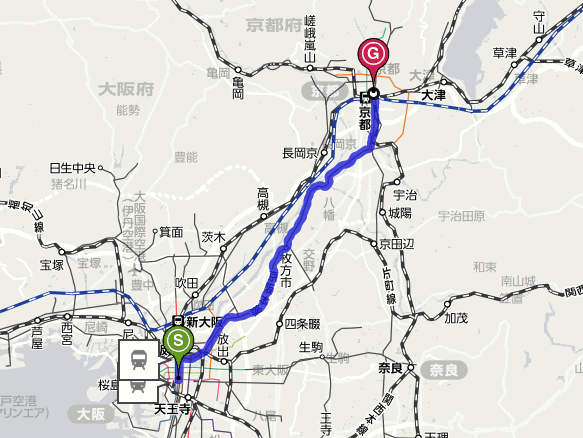
| 【乗車記録】 ・近鉄名古屋6:00→大阪難波8:21 21801 8両 ・なんば8:39→淀屋橋8:44 21813 8両 ・淀屋橋9:00→七条9:42 8107 7両 ・七条9:49→丹波橋10:01 5554 7両 |
⇒次:奈良線は丹波橋駅付近の撮影地で撮影